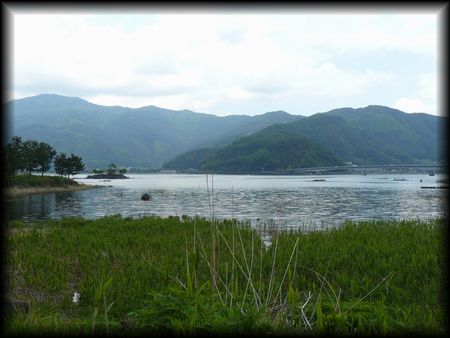|
富士河口湖町(歴史)概要: 富士河口湖町の本格的な開発は奈良時代からで、東海道から分岐し、甲斐国に至る甲斐路(御坂路)が開削されると富士河口湖町には河口駅が設置され重きを成しています(延喜式によると現在の山梨県内には河口駅の他、水市駅、加吉駅が設置されています)。
貞観6年(864)の富士山の噴火により、青木ヶ原溶岩が本栖湖に流れ込み現在の本栖湖・精進湖・西湖が形勢され、多くの人家にも被害をだしています。翌、貞観7年(865)には河口浅間神社が文武天皇3年(699)には冨士御室浅間神社が創建され、富士山信仰の中心地の1つとなりました。
平安時代に入ると荘園開発が進み富士河口湖町では波加利荘や大原荘などが成立しています。この地は甲斐国と相模国、駿河国との国境に近いことから北条氏や武田氏との戦略的拠点となり北条方は御坂城、武田方は本栖城を築いています。又、富士山信仰も盛んになり河口浅間神社の参道には門前町が発達し両側には短冊形地割に御師が建ち並び川口御師として栄えました。
江戸時代に入ると富士信仰の中心が吉田口に移り川口御師は衰微します。又、江戸時代初期は谷村藩に属し、藩主は御室浅間神社と河口浅間神社を保護しています。
富士河口湖町・歴史・観光・見所の動画の再生リスト
|