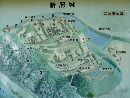|
新府城(韮崎市)概要: 新府城は天正9年(1581)から築城が開始され12月には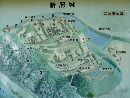 一応の完成したとされる武田勝頼の居城です。天正3年(1575)、長篠の戦いで織田、徳川の連合軍に敗退した勝頼はその後、家臣の離反に悩まし続け、居城である躑躅ヶ崎館(武田氏館)を捨て、新天地ある新府城を居城とし反転攻勢の転機にしたかったようです。躑躅ヶ崎館は甲斐国一国を治めるには問題無かったものの、勝頼の時代には信濃国、遠江国、上野国、美濃国の一部まで版図を広げていた事もあり、それらの領国を結ぶ甲州街道、佐久甲州街道、藤川街道が交差する交通の要衝である韮崎の地に新府城を求めたと思われます。特に、織田家と武田家の経済的に大きな格差があった事から、より経済的に発展出来る要素の強い韮崎が魅力的に映り、さらには信玄時代の旧体制からの脱却が求められました。 一応の完成したとされる武田勝頼の居城です。天正3年(1575)、長篠の戦いで織田、徳川の連合軍に敗退した勝頼はその後、家臣の離反に悩まし続け、居城である躑躅ヶ崎館(武田氏館)を捨て、新天地ある新府城を居城とし反転攻勢の転機にしたかったようです。躑躅ヶ崎館は甲斐国一国を治めるには問題無かったものの、勝頼の時代には信濃国、遠江国、上野国、美濃国の一部まで版図を広げていた事もあり、それらの領国を結ぶ甲州街道、佐久甲州街道、藤川街道が交差する交通の要衝である韮崎の地に新府城を求めたと思われます。特に、織田家と武田家の経済的に大きな格差があった事から、より経済的に発展出来る要素の強い韮崎が魅力的に映り、さらには信玄時代の旧体制からの脱却が求められました。
新府城:上空画像
しかし、木曾地方では木曾義昌、駿河では穴山信君が早々と離反しそれに乗じて木曾、信濃方面から織田勢、駿河から徳川勢が甲斐に侵攻してきます。その際、高遠城(長野県伊那市高遠町)の攻防戦以外は大きな戦いは起こらず、ほとんどの家臣や一族は投降や離散し一気に甲斐まで攻め込まれました。 勝頼は新府城に入城し僅か数ヶ月で家臣である小山田信茂が守る岩殿城へ移り再起を図ろうとしますが信茂の謀反により、死地を悟り武田家縁の天目山の栖雲寺を目指しますが、それも叶わず麓の田野(現在の景徳院の境内)で自害し武田家は滅亡しました。本能寺の変で信長が自害すると旧武田領を巡り徳川と北条の争いとなり新府城は徳川側の戦略上の重要拠点として利用されましたが、領土を掌握すると重要性が失われ廃城となります。 勝頼は新府城に入城し僅か数ヶ月で家臣である小山田信茂が守る岩殿城へ移り再起を図ろうとしますが信茂の謀反により、死地を悟り武田家縁の天目山の栖雲寺を目指しますが、それも叶わず麓の田野(現在の景徳院の境内)で自害し武田家は滅亡しました。本能寺の変で信長が自害すると旧武田領を巡り徳川と北条の争いとなり新府城は徳川側の戦略上の重要拠点として利用されましたが、領土を掌握すると重要性が失われ廃城となります。
新府城は南北600m、東西550mの平山城で東西90m、南北120mの本丸を中心に二の丸、西ノ三の丸、東ノ三の丸、稲荷曲輪、帯曲輪などの主要郭が配置され要所には蔀の構、丸馬出し、三日月堀、枡形虎口などの防御施設を持っています。東堀には東出構、西出構という同時代の城郭では特異な防御施設があり、北方からの攻撃に十字砲火で対応できる備えだったと考えられています。
新府城は武田家最後の城郭として歴史的にも重要で現在でも郭の形状や土塁、堀などの遺構も比較的よく残っていることから昭和48年(1973)に国指定史跡に指定され、平成29年(2017)に続日本100名城に選定されています。又、旧城内には地域の鎮守である藤武神社(平岩親吉が再興)と勝頼の御霊を祭る武田勝頼公霊社が鎮座しています。
韮崎市・歴史・観光・見所の動画の再生リスト
新府城:周辺駐車場マップ
|